
ただし、番号にはなかなか覚えられないという欠点がある。数字には意味がないから覚えにくいといわれることがある。それも確かに一理あるが、私がイスラエルに暮らした経験から言うと、意味は分からなくても、よく通る道の名前はすぐに覚えてしまうものだ。 そもそも名前とはあるものを他のものから識別するためのものなので、意味はとりあえず重要ではない。そのうえ、イスラエルの道の名前はほとんどが人名である。そのため、ユダヤ民族史の知識がないと道の名前は意味のない音の連鎖に過ぎない。
一例をあげると、イスラエルの都市には必ずと言っていいほどヘルツェル通りとヴァイツマン通りがある。ヘルツェルはシオニズム(ユダヤ民族国家樹立運動)の創始者で、ヴァイツマンはヘルツェルの死後にシオニズムの指導者となり、イスラエルの初代大統領となった人物である。これに次いで多いのが、ベン・グリオン(イスラエルの初代総理大臣、建国宣言を読み上げた人物)通り、アルロゾロフ(シオニズムの指導者)通り、ジャボティンスキ(シオニズム右派の活動家)通り、ベン・イェフダ(ヘブライ語復活の立役者)通り、ビアリク(詩人)通りである。もちろん、アインシュタイン通りも存在する。以上はすべて近現代に活躍した人物であるが、旧約聖書の登場人物(ダビデ王、ソロモン王など)や中世の学者(ラムバム、イブン・グヴィロールなど)にちなんだ道の名も少なくない。道の名前になっているのはユダヤ人だけではない。たとえば、バルフォア卿(英国の政治家、ユダヤ民族国家建設を支持したバルフォア宣言を出した人物)通りやエミール・ゾラ(フランスの作家、「私は告発する」によってドレフュス事件の冤罪を指摘した人物)通りがある。イスラエルに来たばかりの私には多くがなじみの薄い名前であった。
意味のない音の連鎖でも、道の名前は案外覚えられる。このことは文化的に重要な意味をもつ。そこに住む者は歴史を学ぶ前から道の名前を通して何十から何百もの歴史上の人物の名前に親しんでいる。そのため、後からユダヤ民族史に触れたときに、それが町内の出来事のように身近に感じられるのである。そういう意味でイスラエルの道は単に場所と場所とつなぐものにとどまらず、過去と現在をもつなぐ存在となっている。そんな道をもつ国を私は今なおうらやましく思う。
(いけだ じゅん)
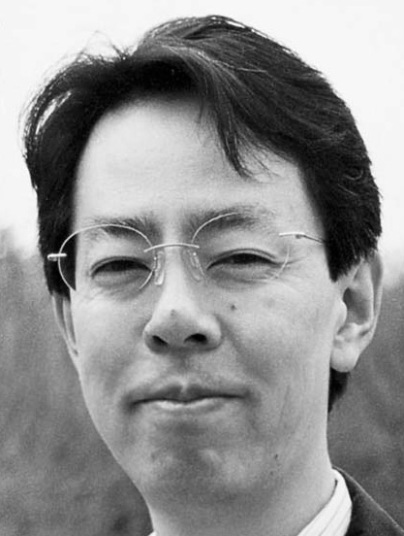
経歴
1983年3月 筑波大学第一学群人文学類卒業
1986年3月 筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科文学修士
1995年7月 テル・アビブ大学大学院博士課程文化科学研究科 Ph. D.
1996年4月 関西外国語大学 外国語学部 助教授
2004年4月 筑波大学大学院人文社会科学研究科 助教授、現在に至る
受賞歴
日本オリエント学会奨励賞(1996年)
主な著書
P. C.クレーギー『ウガリトと旧約聖書』(教文館)1990年4月(共訳書)
D.コロン『古代オリエントの印章』(學藝書林)1998年1月(訳書)
『ヘブライ語のすすめ』(ミルトス)1999年4月
P. ジョンソン『ユダヤ人の歴史』(徳間書店)1999年9月(共訳書)
『ユダヤ教思想における悪』(晃洋書房)2004年6月(共著)
P.ビエンコウスキ他『古代オリエント事典』(東洋書林)2004年7月(共訳書)
その他論文等多数
道経研ウェブサイトに戻る
©Institute of Highway Economics. All rights reserved. <webmaster@ins-hwy-eco.or.jp>